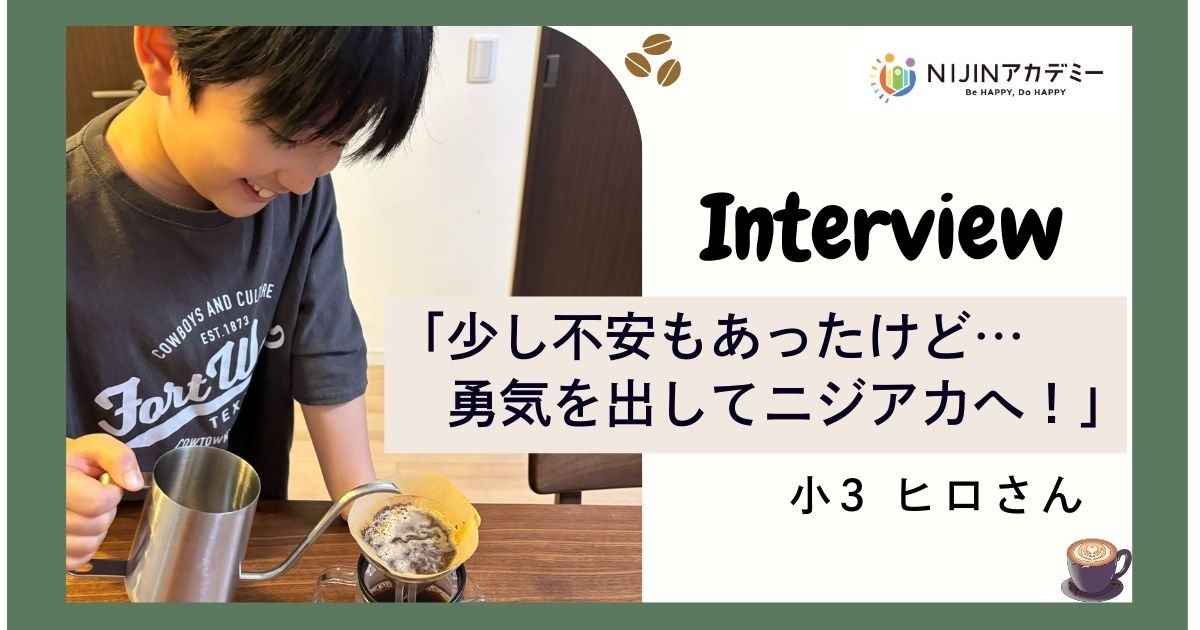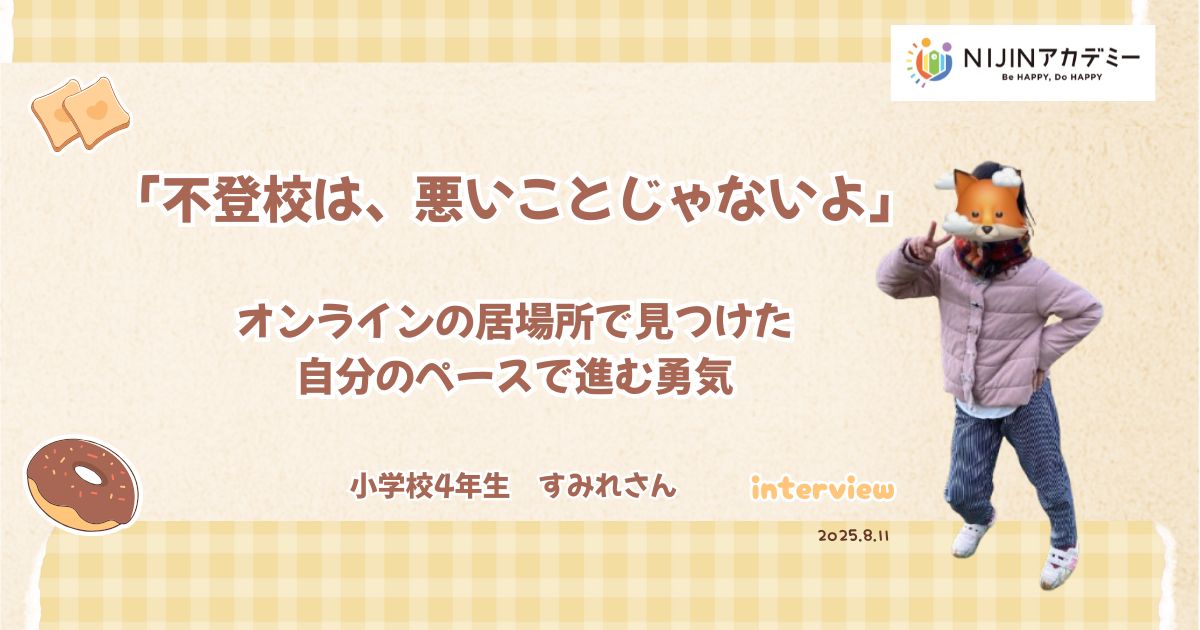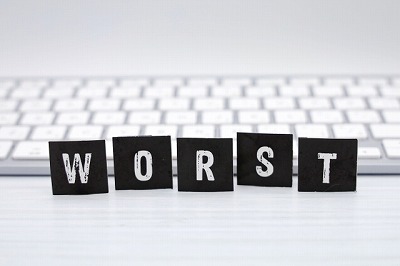「不登校になったのは、私が甘やかしすぎたからではないか」と悩んでいる保護者の方は少なくありません。
しかし、不登校は決して親の甘やかしが原因で起きるものではありません。
不登校の背景には、子ども自身が学校という環境に適応しづらさを感じたり、ストレスや不安を抱えているケースがほとんどです。
この記事では、「甘やかしすぎが原因ではない」という視点から、不登校の原因や子どもへの寄り添い方について詳しく解説していきます。
子どもの判断力を信じ、適切なサポートを行うことで、親としての不安を和らげることができるはずです。
不登校という状況をポジティブに受け止め、一緒に前を向くためのヒントをお伝えします。
不登校と甘やかしすぎの関係についてよくある誤解

「不登校は甘やかしすぎが原因だ」と思われがちですが、これは誤解です。
不登校は単なる親の育て方の問題ではなく、子ども自身が環境や価値観の中で自分なりに判断を下した結果である場合が多いのです。
まずは、この誤解を解きほぐし、不登校を正しく理解することから始めましょう。
不登校は親の甘やかしが原因だという誤解
「不登校=甘やかしすぎ」と捉えられるのは、多くの場合、親が子どもに寄り添いすぎているように見えるからです。
親が不登校の子どもに対して、無理に学校へ行くように指示したり厳しく叱るのではなく、子どもの気持ちや状況を理解しようとしようと次のような行動をとると、周囲から「甘やかしている」と見られやすくなることがあります。
- 子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに、それを否定せずに受け入れる。
- 学校に行けるようになるまで、無理に登校を促さず、家で過ごさせている。
- 子どもが安心できる環境を整えようとしている。
「甘やかしすぎ」と見られてしまう背景には、周囲の「学校に行くのが当たり前」「行かせるのが親の責任」という固定観念があることが多いです。
この観念に基づいて見ると、これらの行動が「甘やかし」と誤解されがちです。
しかし、実際はそうではありません。
子どもが学校に行かない選択をする理由はさまざまです。
例えば、人間関係や学業のストレス、学校そのものが合わないと感じることなどが挙げられます。
親が子どもの意見を尊重し、無理に学校に行かせない選択をしていることに対し、これを「甘やかし」と一括りにするのは、子どもの気持ちや個性を無視することになりかねません。
「甘え」は親子の信頼関係に必要!
「甘え」とは、子どもが親に安心感を求める自然な行動です。
子どもが「学校に行きたくない」と言ったり、「今日は家で休みたい」と言うのは、疲れたり不安を感じたときに親に助けを求めるサインかもしれません。
この甘えは、親との信頼関係を深めるために必要な行為です。
不登校の子どもが親に「甘える」のは、自分の心を守るための大切な行動です。
しかし、この甘えを「甘やかし」と勘違いして、親が子どもに厳しく接すると、子どもが心を閉ざしてしまうことがあります。
安心感を得られなくなり、かえって問題が悪化することもあるのです。
つまり、「甘え」を親が容認することで、子どもが安心して自分の気持ちを表現できる環境を作ることができます。
十分に甘えられることで子どもは安心感や満足感を得られ、心のエネルギーを回復させることができます。
不登校の子どもは自己肯定感が下がっている場合が多いため、焦らず、子どものペースに寄り添いながら待つ姿勢が必要です。
不登校の原因は複雑で多様であること
不登校の原因は一つではありません。
学校でのいじめや人間関係のトラブル、学業のプレッシャー、さらには体調不良や家庭環境の影響など、多岐にわたります。
これらの要因が複雑に絡み合い、子どもが学校に行けない状態になることが多いのです。
こうした背景を理解せずに、「親が甘やかしたからだ」と決めつけるのは間違っています。
まずは、子どもが不登校になった理由をじっくり探り、その中でどんな支援ができるかを考えることが重要です。
他人から「甘やかしすぎ」と言われたとき、親がまず考えるべきこと

他人から「甘やかしすぎ」と言われた場合、親としては戸惑いを感じることもあるでしょう。
しかし、そうした意見に流されるのではなく、親が子どもの状況を正しく捉え、冷静に対応することが大切です。
このセクションでは、親が取るべき考え方について解説します。
子どもの気持ちを最優先に考える
親がまず考えるべきは、子どもの気持ちです。
他人の意見に振り回されるよりも、子どもが何を考え、何に困っているのかを最優先に考えましょう。
子どもの気持ちを理解し、安心感を与えることが、子どもの次のステップにつながります。
他人の意見に左右されることなく、家庭内での子どもの気持ちを最優先にした対応が必要です。
スクールカウンセラーなどの専門家の意見を参考にする
不登校の原因や対応に迷ったときは、専門家の意見を参考にするのも有効です。
スクールカウンセラーや医師、教育相談機関など、専門的な知識を持つ人に相談することで、新たな視点が得られることがあります。
専門家のサポートを受けることで、親も子どもも心の負担を軽減し、前向きに状況を改善していくきっかけがつかめるでしょう。
フリースクールの不登校の親サポートを利用する
フリースクールは、子どもが自分のペースで学び直したり、安心して過ごせる場所を提供しています。
「甘やかしすぎ」という他人の意見に悩んだとき、フリースクールの不登校の親サポートを活用するのも一つの手段です。
これらの場では、不登校や子育てに関する専門的な知識を持つスタッフが相談に乗り、適切なアドバイスを提供してくれます。
不登校「親の会」ネットワークを利用する
全国に不登校の「親の会」があります。
不登校やひきこもりのお子さんを持つ保護者同士が交流できるコミュニティのことです。
同じような悩みを持つ親とつながることで、孤独感や不安を軽減することができます。
不登校の本当の原因を見つけるために知っておきたいポイント

不登校の本当の原因を見つけるためには、子どもとの対話や観察が欠かせません。
ここからは原因を見つける際に親が押さえておくべきポイントを紹介します。
学校での人間関係やいじめの有無を確認する
不登校の原因として、学校での人間関係のトラブルが挙げられることがあります。
友人関係の悩みやいじめがないか、学校と連携しながら確認することが重要です。
また、子どもが何かサインを出していないか、日常の会話の中で注意深く聞くことも必要です。
学業のプレッシャーやストレスを考慮する
学業に関するプレッシャーやストレスが、不登校の一因になっていることもあります。
成績や宿題の負担に押しつぶされている場合、それを軽減する方法を考えることが大切です。
学校の先生に相談し、子どもの状況に合った学び方を提案してもらうのも効果的です。
家庭環境や生活リズムの影響を見直す
家庭の雰囲気や生活リズムも、不登校に大きく影響する要因です。
家庭が安心できる場所であるか、生活リズムが規則正しいかを見直しましょう。
親自身の忙しさやストレスが子どもに伝わっていないかも確認することが大切です。
原因がわからない場合も
不登校の原因は複合的で、本人もわからないということも多くあります。
ただ、漠然とした「学校に行きたくない」にも、「学校に行こうとしたら体調が悪くなる」「授業がつまらない」「周りの子と話が合わない」「ルールが厳しくて嫌」など、何かしらが嫌で、「学校に合わない」状態であることに変わりはありません。
原因をはっきりさせることができなくても、まずは「学校に行きたくない」ことを尊重することが大切です。
甘やかしすぎではない、不登校の子どもに寄り添う具体的な方法

不登校をポジティブに捉えるためには、親が子どもに寄り添う姿勢が欠かせません。
ここからは、不登校の子どもを支えるための具体的な方法を提案します。
子どもの気持ちを受け入れ、共感する
子どもの気持ちを理解し、共感することは、不登校をポジティブに捉える上で非常に重要です。
子どもが学校に行きたくない理由を話してくれたとき、否定するのではなく、共感して受け入れましょう。
共感を示すことで、子どもは安心感を得て、自分の選択に自信を持てるようになります。
無理に登校を強要せず、安心できる環境を提供する
学校に行かないことを責めたり、無理に登校を促すのではなく、家庭で安心できる環境を整えましょう。
子どもが自分のペースで次の一歩を踏み出せるようサポートすることが大切です。
たとえば、好きなことに没頭できる時間を作ったり、親子でゆっくり話をする時間を持つなど、家庭内での安心感を重視しましょう。
子どものやっていることを肯定する
ゲームに没頭して昼夜逆転してしまう、という悩みもよく聞きますが、不登校の子にはよくあることです。
ゲームはやりたいからやっているというより、逃げ場としての機能を果たしていることも。
ゲームの中ではレベルアップすることで達成感を得られたり、ゲーム上での知り合いと会話ができたりするので、心のよりどころとなっていることもあります。
そのため、無理矢理奪ってしまうと余計に精神状態を悪化させてしまうこともあります。
ゲームをやり続けることは子どもの成長に悪い、と考えるのではなく、子どもが何を楽しいと思いゲームをやっているのかなど子どもの理解に繋げると良いでしょう。
選択肢を一緒に探る
無理に登校を促すのではなく、フリースクールやオンライン学習など、学校以外の選択肢を提案してみましょう。
新しい環境が子どもにとって安心できる場となる場合もあります。
子どもの笑顔が増えると親も安心できるので、子どもが居心地が良いと感じる場所を選びましょう。
まとめ:不登校は甘やかしすぎが原因ではない!親が信じるべきこと

この記事は「不登校は甘やかしすぎが原因ではない!子どもの判断力を信じる親の賢い選択とは?」と題してお届けしてきました。
不登校は、甘やかしすぎが原因ではなく、子ども自身が下した大切な判断の結果である場合がほとんどです。
親としては、子どもの気持ちを信じ、環境に合わないと感じたときに「自分の道を選ぶ力」を尊重することが何より重要です。
子どもの選択を否定せず、ポジティブに捉えることで、子ども自身も新たな一歩を踏み出しやすくなります。
親子で信頼関係を深めながら、不登校という状況を前向きに乗り越えていきましょう。